院試対策!勉強はどのタイミングからどのように?
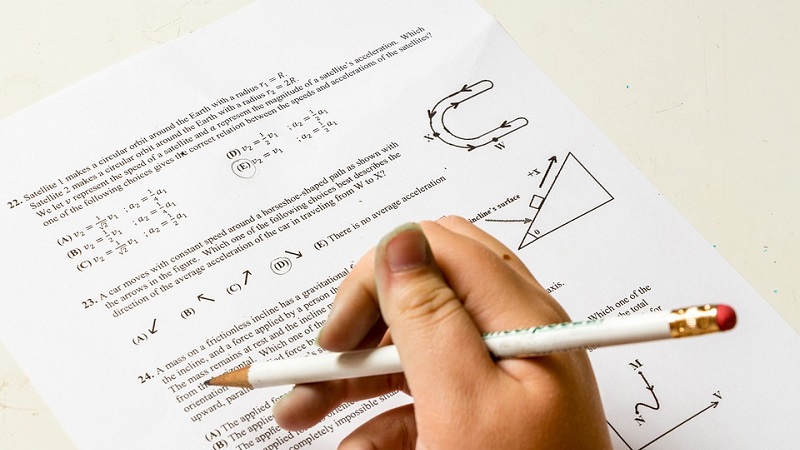

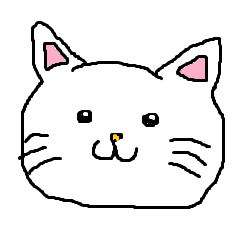
こんにちは、TSです。
大学院では学部に比べてさらに専門的な事を突き詰めていくことが可能となります。
そのため卒業後のキャリアも広がり、大学側でも院に進学することを強く勧めている大学が増えてきました。
しかし大学院も行きたいと思えば簡単に入れるわけではありません。まずは院試を突破する必要があります。
筆者は北海道大学の工学部を学士で卒業し、その後数年間一般企業で働いた後改めて院に行きたいと思い院試を受けました。
今回はその時のことを振り返ってどのように試験対策を行って言ったか、勉強したかを書いていこうと思います。
特に一度社会人になってから受験しなおす方や、多大の院を受ける場合に参考にしていただきたく思います。
大前提

院試を受ける大前提としていくつか気をつけておくべきことを書いておきます。
過去問を手に入れる
院試も通常の受験同様、大学によって傾向や癖があります。
従って勉強をするのも当然過去問がベースになり、そこから分析してどういった問題が出るのか、どの手法で解ければいいのかを研究していかなければなりません。
過去問の入手に関しては研究室訪問で直接貰う、サイト上に転がっているものを利用する、予備校で収集する等いろいろ挙げられますが、自分がどういった経歴があり何故その院を志望するのかを研究室の教授に知ってもらうと言った観点からも研究室訪問を通じで入手するのが一番だと言えます。
多大や自分の所属していない研究室へのアポイントの取り方や研究室訪問の仕方は下記に書いてあるので参考にしてみてください!
問題の特徴を掴む
ある程度過去問を解いたら問題の特徴が見えてくると思います。
ただし全く同じ問題が出ることはあまりなく、表現を変えたり同じ分野でも今までに扱っていなかった問題も当たり前のように出てくるのでそこからさらに展開して対策をしていく必要があります。
筆者の場合ですと試験科目は数学と専門だったのですが、数学は線形代数か微積・微分方程式が毎回出ていたのでその辺を一通り攫い、専門は後述する授業用の教科書を使用しました。
授業で使われていた資料・教科書を入手する
何よりも授業で使われていた資料から問題が出題されることが多いので、その資料をあらかじめ入手出来てしまえばかなり有利になると言えます。
ではその資料はどうすれば入手できるのかという点ですが下記のような流れで筆者は入手しました。
- 受験大学院の学部で受ける授業・担当教授を把握する(各大学のHPに載っているカリキュラム等)
- シラバス検索で参考図書を確認する
- 無かった場合は担当教授のHPを漁る(意外と出てきます)
- それでも足りない分は大学の生協の参考書コーナーを物色
ここまでする必要があったのかは分かりませんが、院に行くためにはやりすぎても十分ということはまずないので徹底的にどん欲に収集していきましょう。
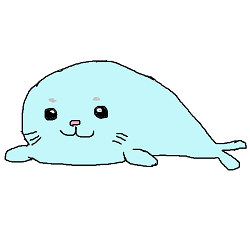
どれくらい取れればOK?
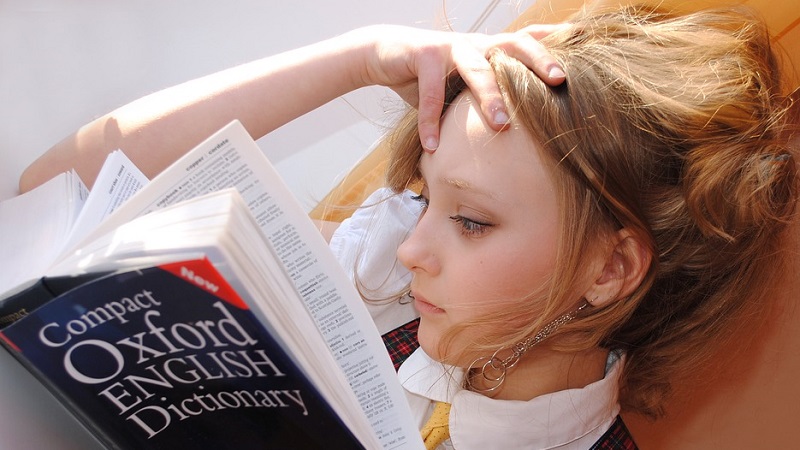
次に大体どのくらい正解すれば良いの?と言った疑問もあると思います。これにも筆者の体験談と教授から実際に教えて頂いた情報を記載していこうと思います。
平均6割
大体はどの院も6割取れれば一安心と言われています。
大学の各単位の合格点も60%以上が可と定められているところが多いのではないでしょうか。
ただし注意して頂きたいのが、合格の基準は大学院によってまちまちという点です。
研究室によっては形式的に試験をしているだけの所もあればガッツリ閾値を設けてその点数に満たない受験者は斬るところもあり、面接での加点が大きいところもあります。このページの情報だけをうのみにせず、受験予定の研究室の先輩や教授から情報を得たほうが明確な答えを得られます
準備をしていないと満点でも落ちる!?
どんなに院試の結果が良くても面接と研究室訪問をしていたかどうかによって結果は左右されることがあります。
例えばあなたが研究室の教授だったとして、受験しに来た方が点数は良いものの普段の素行がサイコパスで平気で危ない事を口にするような方だったらどうしますか?
研究室の空気も乱れますし、大きなもめ事を起こされると自分の研究すらも危うくなるのでまず採用しないのではないでしょうか。
また、そのようなことがなくても研究室訪問をされていない見ず知らずの方が自分の研究室に入りたいと言ってきてはどうでしょう。
研究室には大抵学士4年から入ってくる学生が多く、枠は内部生で埋まっていることもあります。
今まで面倒を見てきた内部生を取るか、成績は良いものの素性も知らないいきなり現れた外部性を取るかと言った場合大抵は前者を取るのではないでしょうか。
そういった面からも予め研究室訪問はしっかりとして置き、面接の対策もしておくことが望ましいです。
英語は?
英語は各大学で独自に試験を設けているところもありますが、国立大学は大抵TOEICのスコアシートを提出すれば良いとされています。
TOEICの点数の基準も大学ごと、研究室ごとにまちまちで換算率も不明確ですが、高得点を取っておくに越したことはありません。
因みに筆者は600点で通過し、先輩には400点代でも通過した猛者が居るそうな・・・
600点くらいなら2~3ヵ月あれば未学習からも持っていけるので、早い段階で勉強を始めておきましょう!
LIFETIME-LEARNER様にてTOEICで600点を目指す為の流れが書かれているため、併せてご覧になって下さい!

定員・倍率はあまり気にしない
通常の大学受験ですと定員が決まっており倍率も3.5倍!などと出て何人落ちるのかが明瞭になってきます。
ただし院の場合は定員はあくまで出しているだけで実際に入学する人数と乖離があります。筆者の受験したコースも毎年45人が定員で合格者数が60人を超えると言ったわけのわからない事態になっているので。
実際に教授に聞いてみたところによりますと、「一応定員は決める、けど優秀な人が来ればその分枠は増やす」とのことだったので、まずは受験者の母集団から外れないように頑張れば問題なく通過するとみて良いでしょう。

勉強を始めるタイミングは?
次に院試の勉強を始めるタイミングです。
専門科目は2ヵ月前
専門科目は自分がすでにその道の勉強をしており、基礎知識が出来ている場合は2ヵ月前くらいから本腰を入れて勉強し始めれば十分に間に合います。
寧ろそれよりも前に始めてしまうと中だるみし、効率が落ちてしまうこともあります。(筆者がそうでした)
ただし、全く別の分野に挑戦する、自分が未経験だった院を受験する場合は2ヵ月では足りません。
科目数にもよりますが基礎をつくるのにはかなり時間がかかるので受験を決めた段階で勉強を開始しましょう。
TOEICは早めに
TOEICはスコアシートを提出するのですが、提出期限は院試当日ではなく願書提出時になります。また、TOEICを受験してからシートが届くまでにも1ヵ月はかかります。
そういった背景もあるのでTOEICは早めに何度か受けておくと良いでしょう。
TOEICも一種の慣れで回数をこなせば点数は上がっていきます。万が一下がってしまっても受けた中で一番良かったものを提出すればよいので回数が多いほど当然有利になります。
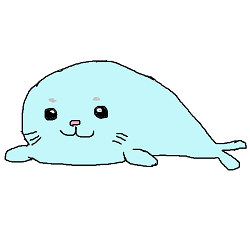
おすすめの勉強場所3選
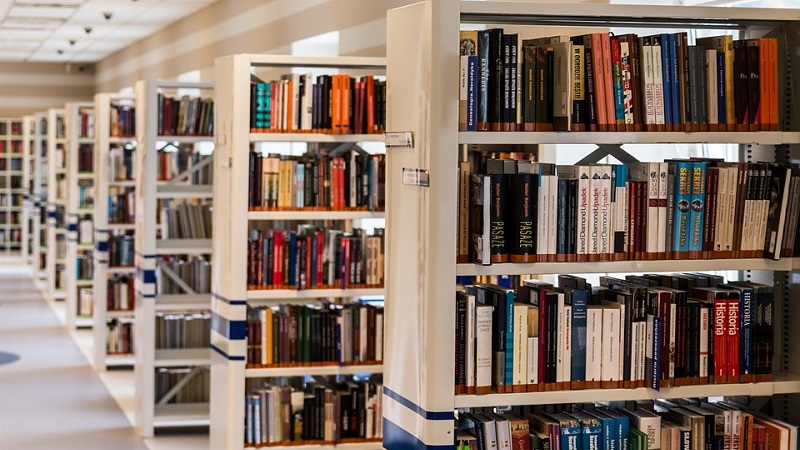
最後に、院試の勉強をするのにうってつけの場所を3つ程ご紹介して締めにしようと思います。
図書館
勉強の王道と言えば図書館ですよね。
静かで周りの人たちも勉強しているので長時間勉強するにはうってつけの場所になります。
カフェ
図書館は静かすぎてなかなか喋れない、友だちに教えてもらいながら(or教えながら)勉強したい!と言った場合はカフェもおすすめです。
同じように勉強している学生も時期によっては居るので、闘争心が芽生えて勉強に身が入りやすくなります。
ただし混雑時に席を占領してしまったり、大声で騒いでは店側に大迷惑です。まわりに迷惑を掛けない最低限のマナーは守りましょう。
職場
意外と筆者が勉強できたのが職場です。
仕事に行く時間を少し早くして朝の始業までの時間を作り勉強したり、昼休みを有効活用することでも勉強が捗ります。
特に社会人になると家と職場の往復しかしない、それでいて家では誘惑が多すぎて勉強できないと言った方は職場の休み時間も有効な時間になりますよ!
もちろん、業務時間中にはダメですよ?(と言いつつネットで数学のサイト見てました・・・w)
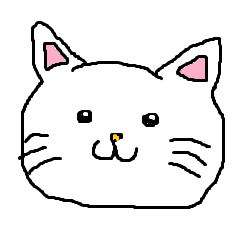
まとめ
今回は院試における勉強や対策をまとめました。
どの大学院も筆記試験の通過率は基本的に8割前後と言われていますが、サボれば痛い目にあいます。
そうならないためにも段取りよく準備をし、万全の状態で受けられるようにしましょう。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません