院試の面接を攻略!合格のフラグ等も紹介!




こんにちは、TSです。
大学院試では筆記試験だけでなく面接もあり、受け答えが酷いと容赦なく落ちます。
せっかく筆記で突破できても面接で落ちてしまっては悔いても悔いきれないと思うので今回は面接の対策方法をご紹介していこうと思います。
院試における面接の目的
院試における面接の目的や位置づけを説明します。
ミスマッチを防ぐ
第一の目的はミスマッチの防止です。
受験者が研究したい内容を志望している研究室で本当に研究できるのかを再確認します。
どんなに素晴らしい研究案があっても研究室でできなければお互い不幸になるだけです。そういった意味でも事前に研究室訪問を行い、自分のしたい研究が本当にできるかどうか確認しておきましょう。
当然点数がある
面接は別名口頭試問とも呼ばれておりれっきとした試験です。
そのため当然評価があり点数をつけられます。
特に口頭で●●の定理を説明してくれ等を聞かれた場合は正しい知識を持っているか、それを論理的に説明できるかも見られています。
どんな問題が出るかは院や研究室によって変わりますが、過去の問題を把握して分析したうえで答えられるようにしておきましょう。
採点はすでに終わっている?
採点は面接時にはすでに終わっていることが多くその点数を前提に面接が進むこともあります。
どこが出来た、出来なかっただけでなく、出来なかった問題に関して踏み込んで聞かれる場合もあるので筆記試験でできなかった方はそのままにせず答えられるようにしましょう。

面接の流れ
当日の面接の流れです。
服装
服装はスーツが無難でしょう。筆者の場合も周り全員スーツでしたし、院によってはあらかじめスーツ着用の事と記載されている場合もあります。
時間
時間は短い場合では5分程、長い場合では40分程と幅が広いです。
短くてもそれは合格が決まっていて既に聞くことがない場合とハナから取るつもりがない場合もあるので時間によって合否を判断するのは難しいでしょう。
合否のフラグについては後ほど書いていきます。
呼ばれる順番
呼ばれる順番は受験番号順の時もあれば五十音順の時もあります。
また、外部入試でその人の事を良く知りたい場合やボーダーラインぎりぎりで長くなりそうな人は後の方で呼ばれる傾向が高いそうです。
形式
形式としては受験者1人~2人VS教授陣複数人と言ったリンチ形式です。
一見プレッシャーが半端ないですが、質問するのは司会進行人の教授と受ける研究室の教授が基本ですのであまり気にしなくて大丈夫です。

しておくべきこと

面接に備えてしておくべきこともさっとまとめておきます。
卒論の見直し
自分が学部生の時に発表した卒論の内容はあらかじめ確認しておきましょう。
学部から院でコースを変える場合でも聞かれることがあるので誰でも理解できる程度にざっくりと答えられるようにしておくとよいです。
院によってはホワイトボードやレジュメを用いて説明させるところもあるそうなので、そういう情報がある場合はシミュレーションしておくことも重要です。
筆記試験の見直し
筆記試験が悪いと改めて解けなかったところに関して突っ込まれることが多いそうです。
筆記が終わってから面接までの間に理解できなかったところを理解しようとする姿勢があるかどうか問われており、これも試験の一環なので、筆記試験が終わったからと言って過去の事にせず、出来なかったところは徹底的に洗い出し完璧に答えられるようにしましょう。
論文を読む
志望する研究室の担当の教授の論文は読んでおきましょう。
そうすることで志望理由を再確認できるので、面接の時にも軸を安定した受け答えが可能となります。
研究計画書を作り込む
研究計画書は願書とともに提出すると思いますが、それを元に面接が進むこともあります。
研究計画書に不備があるとほぼ間違いなく突っ込まれるので研究計画書を書いた段階で担当教授に見てもらうなどして完璧に仕上げましょう。
当日の日程確認
受験票と一緒に送られてくる案内や大学院のHPには面接日の日程や場所が記されていると思います。
試験を申し込んだその日からしっかりと把握し、当日の前日に慌てないようにして当日も遅れないように注意しましょう。
筆者が受験した際には寝坊して面接に間に合わず不合格になっていた方もいらっしゃいました。
その方は学部の成績が非常に優秀で筆記試験が免除になっていたのですが、成績に関係なく一発outだったそうです。そういったミスを起こさないためにもしっかりと資料を読み込んでスケジュール管理を徹底しましょう。
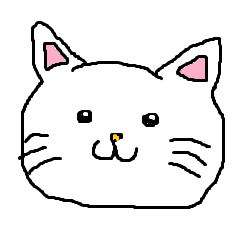
聞かれる事一覧・具体的な回答

実際に院試で聞かれたことや、周りの方で聞かれた内容を一覧としてご紹介します。
志望動機
多分どの院のどの研究室でも聞かれるのではないでしょうか。
回答の流れとしては「現状の問題点提起→先行研究→改善策となる研究手法を提示」と言った流れで回答しましょう。
ただしその研究手法が2年ないしは5年で終わるかどうかも事前に見通しを立てておく必要があります。
博士課程に進むのか
修士を2年で卒業した後に博士課程にも進むかどうか聞かれることがあります。
現在大学院では博士まで進む方が少なく人手不足が叫ばれているので博士課程まで進みたいと言った方は大歓迎だそうです。
従って博士課程を考慮している場合はどうどうとそのことを伝えましょう。
また、博士に行くつもりがなくてもスッパリと行かないと言い切ってしまうのは良い印象ではありません。
現在迷い中だとかその時になって研究状況を見て考えたいなど暈して答えると良いでしょう。
卒論のテーマ
先述の通り卒論で何を研究し発表したか聞かれることがあります。
ざっくりと2~3分で完結に答えられるようにまとめておきましょう。
試験の出来具合・試験に関係する問題
試験ができたかどうか聞かれることもあります。
嘘ついても仕方ないのでどこが出来たかできなかったか素直に答えましょう。
入学後にしたいこと
入学後にどのような研究がしたいかを聞かれる場合もあります。
志望理由と似通ってはいますが、その研究が希望している研究室で出来る研究かどうかのリサーチは忘れずにしておきましょう。
また、研究には基礎研究と応用研究があります。そのどちらがしたいのかも明確にしておくと良いでしょう。
卒業後に何になりたいか
卒業後の進路です。就職したいのか大学に残りたいのかなどの意思確認ですが、どちらが良いと言った答えはないので思ったように伝えましょう。
最近妻に嫌われているのだがどうすればよいか
筆者の先輩が所属する研究室の準教授からの質問だったそうです。
面接というよりほぼ人生相談ですね・・・w
このような質問をするおちゃめな教授も居ますが、場を持たせるためのやり取りなので適当にあしらっておきましょう。
筆者の大学でこういった質問をされた方はほぼ100%合格していたのでそもそも筆記が優秀過ぎた、成績がトップレベルなので試験をするまでもない方がこういった質問を受けるらしいです。
因みに先輩曰く大学生活以降での最大の難問だったそうな・・・。
落ちたらどうするのか
落ちたら他の院に行くのか、就職するのかなども聞かれることがあります。
この質問に対しての返答としては他の研究室も考慮しているなら素直にそのことを述べ、後期(二次募集)があるならそれを受けると言った意気込みがあるならそちらも伝えておくと良いでしょう。
学費はどうするのか
筆者が受けた質問ですが、社会人になってから受験したり所帯持ちだったりするとこの質問が来ます。
貯金をしているならその旨を、親からの援助が期待できるならそれも良いでしょう。
因みに筆者はサイトからの収益でとドヤ顔で答えたら教授が苦笑していたのを覚えています。

合格・不合格フラグ

先輩や自分の経験を通して、この質問がされたら合格の確率が高い、不合格の確率が高いと言った指標を紹介します。
ただしもちろん例外もあるので鵜呑みにはしないでくださいね。
合格フラグ
まずは合格フラグです。
その場で合格を言われる
研究室の方針によっては結果は合格発表日まで言わないといったところも多いですが、中には面接の場で合格を宣言する所もあるそうです。
これはフラグというよりそのまま結果ですね。
院に入った後の事を聞かれる
院に入ったら何をしたい、何になりたいを聞かれた場合も合格の可能性が高いです。
これは最終的な意思確認と取ることができて、教授から「では〇〇の研究がしたいということで良いですね?」と念を押されるような形で確認されればほぼほぼ合格でしょう。
不合格フラグ
次に不合格フラグです。
落ちたらどうするのかを聞かれる
現在志望している研究室がダメだったときはどうするか聞かれるようなことがあればほぼほぼ落ちるそうです。
院で一浪した先輩方ももれなく聞かれたそうで、後期で頑張ります!と強い意志を見せてもダメだったそうな。
他大の併願状況を聞かれる
これもあまりよい結果が期待できない時に言われるそうで、教授陣からすればここがダメでも他の受け皿があるかどうかを確認していると言った見方ができます。
ただ逆に、自分の大学で合格を出しても他の院へ行ってしまうのではないかと言った探りを入れている可能性もあるので、上記の落ちたら~よりはまだ希望があります。
判定できない要素
その状況だけでは判断できない要素も書いていきます。
面接時間が短い
面接時間が短いのは単純にその人に興味がないだけで早く切り上げたい場合と、逆に合格が確定しているから今更聞く必要がない場合の二極化です。
今までの研究室訪問や大学の成績、試験の結果等を踏まえて自己判断しましょう。
面接時間が長い
面接が長い場合は受験者が外部入試などで深く知りたい場合や合格ラインすれすれの成績だった場合です。
これは試験の応答次第で合否が決まるパターンなので長丁場になっても集中力を切らさず全力を出し切りましょう。
呼ばれる順番
呼ばれる順番としても上記の通り、早く終わる人が先、長引きそうな人が後となりますが、それ以外にも受験番号の順やエントリー順、名前の順など様々な要因があるので何とも言えません。
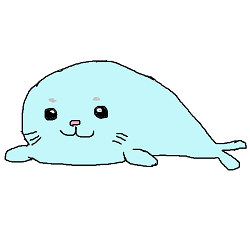
まとめ
今回は面接の攻略法と対策、合格したかどうかのフラグをまとめさせていただきました。
院試は大学受験までと違い情報戦で、単純な成績だけでなく自分が何をしたいのか、何ができるのかと言ったスキル的な面や事前に研究室訪問をして教授と話し合っているかと言った要素も大きく絡みます。
もちろん、試験の出来も大きく絡むので徹底的に対策をして悔いの無い結果を出せるように頑張ってください!
試験対策の記事は下記に纏めています。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません